今月のUTギターズ・ギルド登場
永井龍雲さんのステージを久々に拝見しました。浅草・木馬亭、先週の金曜から日曜までの三日間のイベントでした。
かつて一世を風靡したフォーク・ソングは、時代とともにミュー・ミュージックへ、そしてJポップへと変遷を遂げ、音楽性の技術的側面は以前は考えられなかったほどに高度化しましたが、その一方でフォークが不可避の成分として内包していたスピリット、アーティストが産業の一部としてではなく、あくまで個人として時代と向き合おうとしていた精神は失われていった、と考えるファンも少なくありません。
永井さんのステージはカラオケは勿論、共演者(伴奏者)も一切なく、カバーも基本なく、全て自身の言葉とメロディー、自身が奏でるギターとハーモニカだけで綴られました。
曲間のトークもすべてプロフェッショナルなタレントとしての演出とは違い、永井龍雲(本名だそうです)その人の今、が語られているとお見受けしました。
反戦とか、政治とかを語ることこそありませんでしたが、フォークの精神がこの2018年にも生き続けていることを感じさせるステージでした。
さて、そんな永井さんのステージを支えたのが写真のギルド12弦ギター。メインの6弦はテイラーでしたが、マーティンやギブソンと並ぶアメリカン・アコースティック・ギターの名門・ギルトの響きは、フォークの原点を感じさせる、素朴かつ華麗な響きでありました。

12弦ギターは弾き難く、使い方を選ぶギターです。特に昨今はコーラスなど電気的エフェクトで似た効果を容易く出せるせいもあってあまり流行りませんが、やはり「本物の12弦」でなければ出せない音というものがありまして、じゃらんと鳴らすだけで、フォークやロックが自由な精神を羽撃かせていた時代の空気が蘇ります。
12弦ギターの音は、ブルーズ、ロックやフォークの歴史を何気に彩り、支えています。『朝日のあたる家』(レッドベリー)、『ア・ハード・デイズ・ナイト』(ザ・ビートルズ)、『ミスター・タンブリンマン』(ザ・バーズ)、『天国への階段』(レッド・ツェッペリン)、『ホテル・カリフォルニア』(イーグルス)などは、12弦ギターの音色なしではレジェンドとなり得なかったかもしれません。本邦なら『想い出の渚』(ザ・ワイルドワンズ)や『君のひとみは10000ボルト』(堀内孝雄)を忘れるわけにはいかないでしょうね。
ジャズの世界だって、あのパット・メセニーもそのキャリアの最初は12弦ギター専門要員として、ゲイリー・バートンのグリープに雇われたというエピソードがありますし、ジョージ・ベンソンも初期の名作『バッド・ベンソン』のジャケット写真でエレクトリックの12弦を持っています。
永井さんのライブ・パフォーマンスは「歌手」と云うより「ミュージシャン」のそれでありました。歌とギターが「主役と伴奏」でなく、ひとつの音楽として溶け合っていました。正直、音のバランスとか、テイラーでは綺麗すぎるな、昔みたくギブソンやマーティンを(ヤマハFGでもいいな)、ラインじゃなくマイクロフォンで拾った音で聴きたいな、と思ったんですけどね。
(高村)
歌の手帖 2018年10月号 | 歌の手帖,2018 | 歌の手帖社 utate online


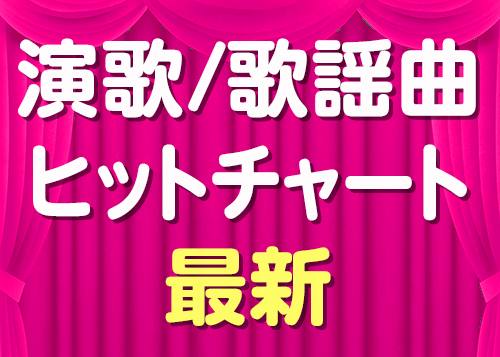



-250x300.jpg)